この記事はで読むことができます。
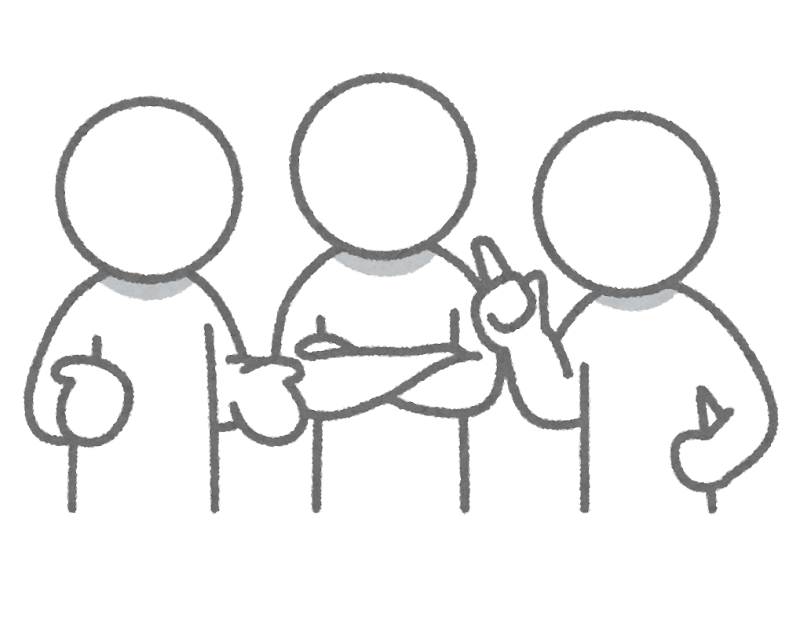
「人間の理解」とは、単に現実の生活状況を把握するだけでなく、その人のこれまでの生活の歴史から未来への志向性(希望)を含めて理解することです。
人は皆、平穏で幸せな生活を送り、「よりよく生きる」ことを望んでいます。
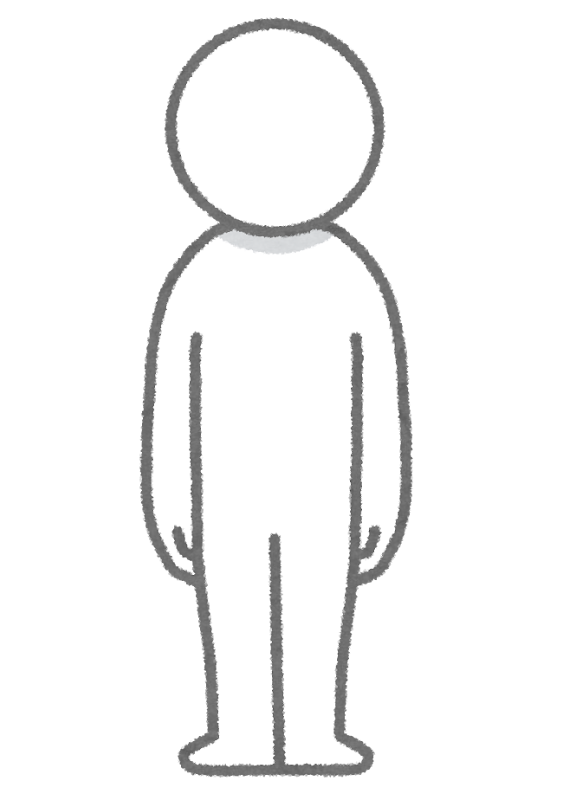
「人間の尊厳」とは、人間が個人として尊重されることを意味する、個人の幸せにとって大切な普遍的な理念です。この理念は、人々の生活の営みにおいて目指すべきものとされており、介護サービスにおける「生活支援技術」もこの理念のもとで行われるべきだとされています。
日本の法制度においても、人間の尊厳は明確に位置づけられています。
- 日本国憲法
・第13条(幸福追求権)は「すべて国民は、個人として尊重される」と定めており、この「個人の尊重」こそが個人の尊厳であり、人権の基本権とされています。これは、個人の生命、自由、幸福追求の権利を保障するものです。
・第25条(生存権)は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、国が社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進に努める責務を負うとしています。

「利用者主体」とは、個人の生き方が尊重され、その人自身の個性が大切にされるという考え方です。
これは、利用者の生活設計を利用者とともに立てていく際に、しっかりと踏まえるべき重要な概念です。
たとえ、どのような状況にある人であっても、その人の人生の主役はその人自身であり、かけがえのない唯一無二の存在であるという認識に基づいています。
この考え方は、2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」にも通じており、障害を個人の問題ではなく、社会の側にあるものと捉え、環境整備や支援を通じてその人らしく生きるための社会条件を改善していくことが役割だとされています。
 kaigo clover
kaigo clover