この記事はで読むことができます。
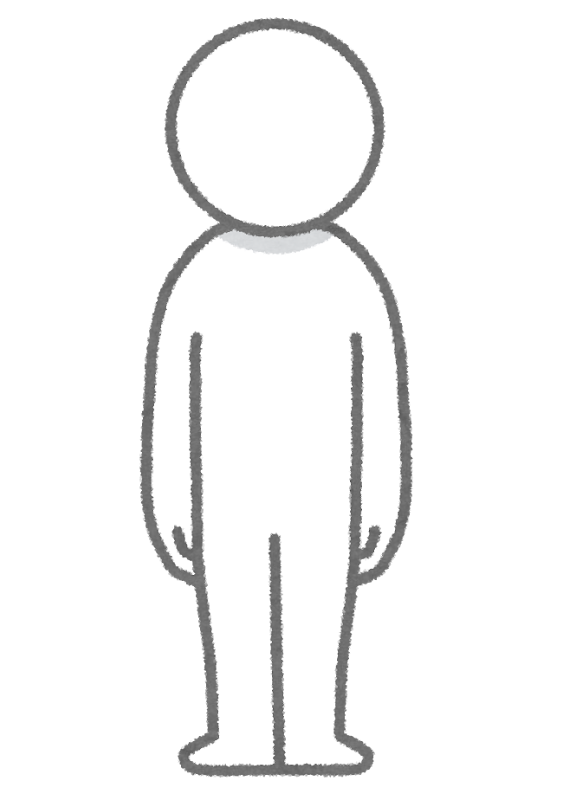
ノーマライゼーションとともに、社会福祉分野の支援に大きな影響を与えた考え方がQOL(Quality of Life:生命・生活・人生の質)です。
QOLという考え方は、1960年代にアメリカの社会学や経済学分野で、国民生活の豊かさを表す概念として使われ始めました。
その後、1970年代後半に医療・リハビリテーション分野へ、1980年代には社会福祉分野へと導入され、新しい価値観を伴う指標として使われるようになりました。
医療分野でのQOL
ターミナルケアの場面で「生命の質」や「人生の質」が問われます。
アメリカでは1975年のカレン裁判を契機に、リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)やアドバンス・ディレクティブが法制化されました。
日本では法制化はされていませんが、厚生労働省が「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を公表しており、ACP(アドバンス・ケア・プランニング:意思決定支援計画)が重視されています。
病状や治療内容について十分な説明を受け、納得した上で治療やケアに同意するインフォームド・コンセントが重要とされます。
最近では、子どもであっても病気や治療について説明を受け、主体的に向き合うことを促すインフォームド・アセントも求められています。
 kaigo clover
kaigo clover