この記事はで読むことができます。
呼吸とは

呼吸
口や鼻から空気を吸い込み、肺から口や鼻に空気を送り、吐き出すこと
呼吸によって体内に取り入れた酸素は血液を通じて全身に運ばれます。
体内で使われた酸素は二酸化炭素となり、血液中に混ざって肺を通じて外部に排出されます。
体内にある酸素と二酸化炭素のバランスが崩れると、健康に支障が出る可能性があります。
正常な呼吸は、生命維持において極めて重要であると言えます。
外呼吸と内呼吸

呼吸には外呼吸と内呼吸の2つがあります。
外呼吸は、肺胞と血液の間で酸素・二酸化炭素を受け渡すことで、
内呼吸は、全身の細胞と血液の間で酸素・二酸化炭素を受け渡すことです。
外呼吸
肺胞と血液の間で酸素・二酸化炭素を受け渡すこと
内呼吸
全身の細胞と血液の間で酸素・二酸化炭素を受け渡すこと
吸った空気は、口・鼻→咽頭→喉頭→気管→気管支→肺→肺胞→血液→全身の細胞へと送られます。
二酸化炭素を体外へ吐き出すときは、この逆の順番で行われます。
上気道と下気道

空気は、口や鼻を通って喉の奥にある咽頭を通ります。
ここまでは食べ物も同じ場所を通りますが、この先は空気と食べ物で通る場所が異なります。
空気は気管に流れていき、食べ物は食道に流れていきます。
この枝分かれをする部分までを上気道といいます。
上気道
鼻腔・咽頭・喉頭までの通り道
枝分かれ部分(喉頭の入り口)には、食物が気道に入らないようにするためにふたがあります。
このふたを喉頭蓋といい、食物が気管に入らないようにする役割があります。
喉頭蓋
喉頭の入り口にあり、食物が気管に入らないようにふたの役割をする部分
喉頭を通過した空気は、気管を通り、左右の気管支に分かれて肺に入ります。
気管と気管支のことを下気道といいます。
下気道
気管と気管支のこと
肺に入った空気は気管支の先にある肺胞に入ります。
換気とガス交換
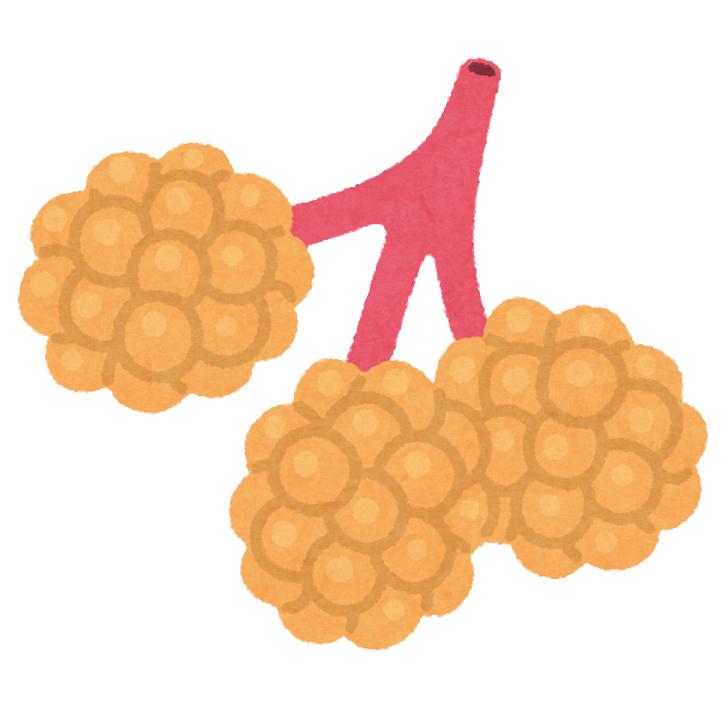
呼吸のはたらきに関わるからだの器官を、呼吸器官といいます。
呼吸器官には、換気とガス交換の2つの役割があります。
換気は空気の出し入れのはたらきであり、ガス交換は肺胞に運ばれた空気と血液との間で、酸素や二酸化炭素の受け渡しをするはたらきをします。
換気
空気の出し入れのはたらき
ガス交換
肺胞に運ばれた空気と血液との間で、酸素や二酸化炭素の受け渡しをするはたらき
換気のはたらきが低下する病気に「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」「気管支喘息」
ガス交換のはたらきが低下する病気に「慢性閉塞性肺疾患」などがあります。
いつもと違う呼吸状態

いつもと違う呼吸状態かどうかは、以下のポイントを確認します。
- 呼吸の回数
- 呼吸の音
- 呼吸の仕方
- 呼吸の苦しさ
具体的に見ていきましょう。
呼吸の回数
正常の場合、成人は1分間に約12〜18回程度の呼吸数が正常です。
体内で酸素がより必要になる場合は、足りない酸素を補うために呼吸回数が増えることがあります。
特に呼吸障害のある人が、運動や入浴をするときには気をつける必要があります。
呼吸の音
正常の場合、「スースー」といった空気が通るようなかすかな音が聞こえる程度です。
体内の空気の通りが悪くなった場合は「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった音が聞こえたり、
痰がからむなどすると「ゴロゴロ」といった音がする場合もあります。
呼吸の仕方
正常の場合、胸部や腹部が呼吸に合わせて一定のリズムで膨らんだり縮んだりします。
体内の酸素が不足していると、呼吸の間隔が長くなったり短くなったりすることがあります。
呼吸の苦しさ
呼吸がうまく行えず、呼吸することが苦しく不快と感じることを「呼吸困難」といいます。
本人が「苦しい」と訴えることが難しい場合や、意識がない場合でも、苦しそうな様子がみられる場合は呼吸困難があると考えて対応をする必要があります。

呼吸の回数、音、仕方、苦しさといったポイントを確認し、いつもと違う様子が見られた場合には医療職に連絡をしましょう。
喀痰吸引とは

痰が溜まっていると酸素をうまく取り入れることができなくなります。
通常はくしゃみや咳払いをすることで体外に排出されますが、老化や病気の影響で自分で痰を出すことが難しい場合もあります。
その場合は、吸引器を使って痰を吸い出します。これを喀痰吸引といいます。
喀痰吸引
吸引器を使って、痰を吸引し取り出すこと
喀痰吸引は、吸引器につないだ管(吸引チューブ)を口や鼻から挿入して、痰を吸い出します。
介護福祉士が行える喀痰吸引では、吸引チューブを挿入する場所は、3つに分かれます。
- 口腔内
- 鼻腔内
- 気管カニューレ内部
口から吸引チューブを挿入する場合を口腔内吸引、鼻から挿入する場合を鼻腔内吸引、気管カニューレから吸引する場合を気管カニューレ内部吸引といいます。
口腔内・鼻腔内の吸引では「咽頭の手前まで」、気管カニューレからの吸引では「気管カニューレ内部」までと、吸引チューブを挿入できる範囲が限定されています。
また、喀痰吸引は医行為であり、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」とされています。
よって、介護福祉職が喀痰吸引をする場合には、医師の指示書が必要となります。
喀痰吸引が必要な状態

喀痰吸引が必要な状態について、以下のポイントを確認しましょう。
- 痰が増加している状態
- 咳の力が弱く、痰を出しにくい状態
- 痰が固くなり、出しにくい状態
具体的に見ていきましょう。
 kaigo clover
kaigo clover