ペースメーカーは、心臓がうまく働かない人の体に埋め込む機械で、心臓の動きを助ける役割があります。
ペースメーカーを使用することで、ほとんど今までと変わりない生活を送ることができますが、日常生活を送るうえで、注意すべきことがいくつかあります。
今回は、ペースメーカーの役割と、装着している人が注意することについて確認していきます。
心臓の働き
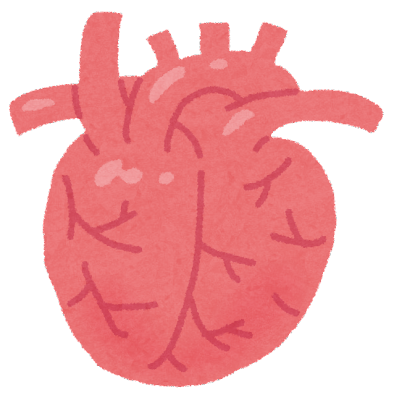
まずは心臓の働きについて確認しましょう。
心臓は、規則的に拍動することで、からだ全体に血液を送り出すポンプのような役割をしています。
このポンプを動かしているのは電気刺激で、右心房の上部にある「洞結節(どうけっせつ)」とよばれる場所から信号が送られています。
「自然のペースメーカー」ともよばれるこの洞結節が、ごく弱い電気信号を規則的に出すことで、心臓の筋肉は収縮し、血液をからだ全体に送り出しています。
対象となる不整脈
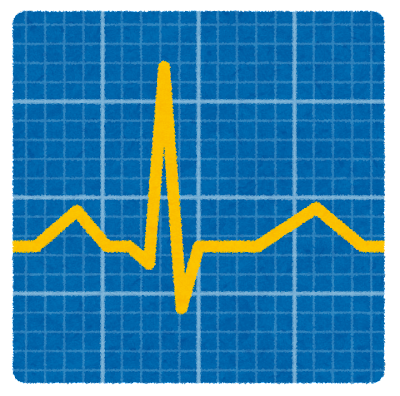
正常な心臓では、電気信号が一定のルートで伝わることで、心臓の筋肉が収縮し、からだ全体に血液を送り出しています。
しかし、病気などが原因で別の場所から電気信号が発生したり、送られた電気信号がルートのどこかで伝わらなくなってしまうことがあります。
こうなると、心臓の拍動のリズムや回数が一定でなくなってしまいます。
この状態を、「不整脈」と呼びます。
不整脈は、大きく3つのタイプに分かれます。
- 頻脈(脈が早くなる)
- 徐脈(脈が遅くなる)
- 期外収縮(脈が途中で飛ぶ)
特に、ペースメーカーで治療が必要となるのは徐脈です。
徐脈が起こっている間は、拍動が減り、血液を送り出す回数が減ってしまいます。
そのため、酸素を含んだ血液が脳まで十分に送られなくなり、めまいを起こしたり、場合によっては失神することもあります。
こういった心不全の症状をともなう「徐脈性不整脈」の治療にペースメーカーは使用されています。
診断名と症状

代表的な診断名は以下のとおりです。
房室(ぼうしつ)ブロック
洞不全(どうふぜん)症候群
房室ブロックでは、電気信号が通るルートが障害されており、うまく電気信号が伝わりません。
洞不全症候群では、心臓の電気信号を作る「洞結節」が正常に機能しなくなります。
結果として、心臓に電気信号が伝わらないことで、徐脈となります。
原因としては、加齢や心筋梗塞といった「心臓病」や、「薬剤の副作用」などがありますが、多くの場合、原因は明らかではありません。
主な症状は以下のとおりです。
徐脈による脳虚血→ふらつき、失神
心不全症状→息切れ、倦怠感、浮腫
ペースメーカーの埋め込みには、「徐脈」とそれにともなう「症状」があることが条件です。
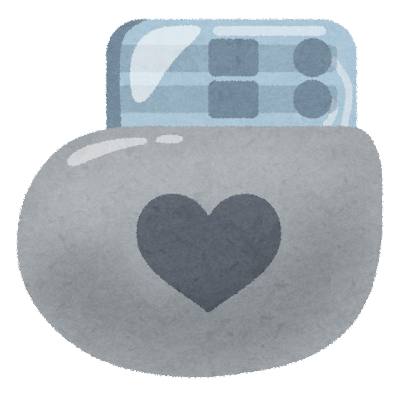
ペースメーカーの役割
ペースメーカーは、脈拍が決められた一定以下になったときに刺激を送れるように、電気信号を24時間監視しています。
そして、必要なときには心臓の筋肉が動くように電気信号を送ります。
心臓の徐脈性不整脈の監視
電気信号の送信
ペースメーカーは、脈拍が決められた一定以下にならないように心臓に刺激(電気信号)を送っています。
ペースメーカーの構造
ペースメーカーは、電気信号を作る本体(ペースメーカー)と電気信号を伝えるリード部分(導線)に分かれています。
本体には、電池と電気回路が内蔵されており、その上部にリードをつなぐ部分があります。
本体から送り出された電気信号は、リード線を通って心臓に伝わります。
電池の寿命は約5〜10年となっています。
ペースメーカーの埋め込み
ペースメーカーとリードのどちらも、手術によって体内に完全に埋め込まれます。
埋め込み場所は、胸部(鎖骨の下)か腹部のどちらかになりますが、
一般的には、胸部(鎖骨の下)を通る静脈にリードを挿入する方法がとられます。
多くの場合、左鎖骨の下方に埋め込まれることが多いため、更衣や入浴の際に確認しましょう。
日本での装着者数
日本では、毎年約4万人が新たにペースメーカーの埋め込み手術を受けており、累計では約40万人ともいわれています。
装着者の平均年齢は74歳で、そのうち約90%が65歳以上の高齢者となっています。
一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会 都道府県別ペースメーカ、CRT-P植込台数 年次推移

ペースメーカーの埋め込み手術から、退院後に必要となる定期検診といったスケジュールについても確認しておきましょう。
心電図モニターの装着、入院生活と手術の説明、同意書の提出などを行います。
一般的な手術の場合は、胸部への局部麻酔。手術時間は1〜2時間程度です。
ペースメーカーのチェック、傷の状態の確認、退院後の生活指導などを行います。
埋め込んだリードが安定するまでは、上腕を激しく動かしたり、重いものを持つといった動作は控えます。
身体の状態やペースメーカーの作動状況、電池の残量、リード(導線)の異常の有無など確認します。
リードに問題がなければ、電池が内蔵されている本体部分の交換のみで、翌日には退院できます。
ペースメーカーの埋め込み手術が終わった後には、定期検診と電池交換が必要になります。

ペースメーカーを使用することで、ほとんど今までと変わりない生活を送ることができますが、注意すべきことがいくつかあります。
ペースメーカーは超小型のコンピュータのようなもので、外部からの電気や磁力に影響を受けることがあります。
影響があるもの
体脂肪計
金属探知機
電子商品監視機器(EAS)
マッサージチェア
アマチュア無線
全自動麻雀卓
電気自動車の急速充電器

空港で保安検査を受けるときには、ペースメーカー手帳を係員に提示して、金属探知器を用いない方法で検査を受けましょう。
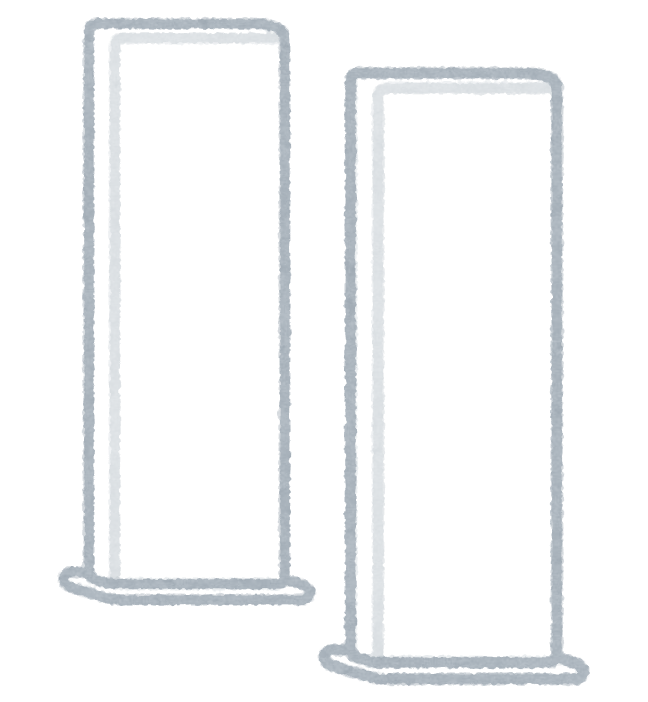
また、お店や公共施設の出入口に設置されている盗難防止装置(EAS:電子商品監視機器)を通るときには、立ち止まらないで中央付近を速やかに通り過ぎるようにします。
MRI ※機器によっては可
CT
放射線治療装置
体外式除細動器(AEDなど)
電位治療器
高・低周波治療器

※ペースメーカーの種類によっては、MRI検査に対応できるものがあります。

AEDの電極パッドには、胸の右上部分と左脇腹にパッドを貼る図が記載されています。
ペースメーカーの真上に電極パッドを貼ってしまうとペースメーカーが故障する場合もあるため、電極パッドはペースメーカーの真下に貼りましょう。
注意事項を守れば、安全に使用できるもの
携帯電話
IH調理器/炊飯器

ペースメーカーから15cm以上離し、反対側の耳に当てて使用しましょう。
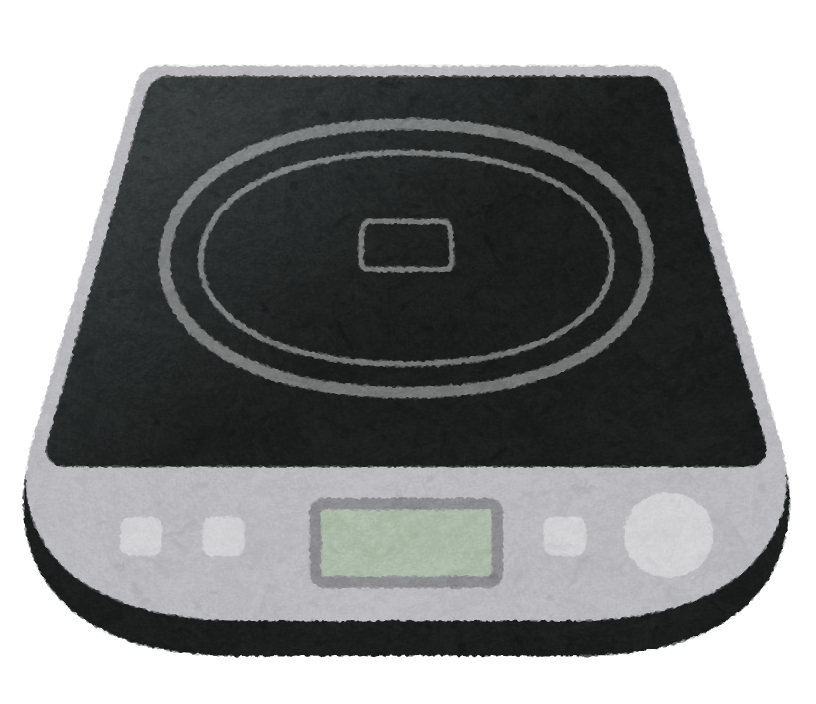
ペースメーカーの埋め込み部位が近づかないようにしましょう。
モニター、モニター使用機器
配電/分電盤
一般的に影響が少ないもの
冷蔵庫/食洗機/洗濯機
テレビ/パソコン
電子レンジ
電気毛布/敷布団
電気こたつ/ホットカーペット
温水洗浄便座
電車
電動式自転車/自家用車
補聴器
血圧計
体温計
心電図
電動工具

ペースメーカーから15cm以上離し、反対側の耳に当てて使用しましょう。
| 家庭 生活 | ・マッサージチェア ・体脂肪計 ・金属探知機 ・電子商品監視機器(EAS) ・電位布団 ・家庭用ジアテルミー(電気治療機) ・全自動麻雀卓 ・電気自動車の急速充電 | ・携帯電話 ・IH調理器/炊飯器 | ・冷蔵庫 ・食洗機 ・洗濯機 ・テレビ ・パソコン ・電子レンジ ・電気毛布/敷布団 ・電気こたつ ・ホットカーペット ・温水洗浄便座 ・電車 ・電動式自転車 ・自家用車 |
| 医療機器 | ・MRI(機器によっては可) ・放射線治療器 ・電気メス ・体外式除細動器(AEDなど) ・電位治療器 ・通電鍼治療器 ・高/低周波治療器 | ・補聴器 ・血圧計 ・体温計 ・心電図 | |
| 工業機器 施設 | ・アマチュア無線機 ・業務無線 ・発電施設、変電施設 ・溶接機 ・電磁石 | ・モーター/モーター使用機器 ・配電/分電盤 | ・電動工具 |
ペースメーカーを使用することで、ほとんど今までと変わりない生活を送ることができますが、注意すべきことがいくつかあります。
場面ごとに確認しましょう。
運動
手術が終わり、埋め込んだリードが安定する数カ月後には、ほとんどの運動をすることができます。
しかし、ペースメーカーに近い筋肉である上腕を長時間動かしたり、激しく身体がぶつかる運動は、ペースメーカ本体にダメージを与えたり、リードが損傷する可能性があるため、控える必要があります。
入浴
入浴がペースメーカに直接影響を与えることはありません。
長時間、熱い湯に入ることで脈拍が上昇し、心臓に負担がかかるため、入浴時間は短めにするといった配慮が必要です。
また、低周波電流が流れている電気風呂は、ペースメーカに影響を与えるため、利用は控えましょう。
旅行
電車や自動車、飛行機、客船といった乗り物に制限はありません。
しかし注意すべきポイントがいくつかあります。
・エンジンのかかっている車のボンネットを開けて、エンジン部分に身体を近づけないようにしましょう。
・ペースメーカーの埋め込み部分をシートベルトで圧迫しないようにしましょう。
・電気自動車の急速充電器は使用しない、設置場所には近づかないようにしましょう。
・スマートキーシステム(キーを持っているだけでドアロックが解除できるシステム)のアンテナから、ペースメーカ本体まで、22cm以上離れるようにしましょう。
・空港の金属探知機に反応することがあるので、ペースメーカ手帳を係員に提示しましょう。
第33回 障害の理解
問題94 心臓機能障害のある人に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
塩分を過度に摂取することで、体内を循環する血液量が増え、心臓に負担がかかります。
よって、心臓機能に障害があつ人には、塩分の制限が必要な場合があります。
心臓機能の障害がある人は、慢性心不全を起こしている場合が多く、呼吸困難や動悸、息切れといった自覚症状がみられます。
呼吸困難や息切れといった自覚症状がみられますが、外出を避ける必要はありません。
医師と相談した上で、適度な運動を行い、残存機能を維持することが必要です。
ペースメーカーの装着者は、身体障害者手帳の障害等級1、3、4級に該当します。
よって、身体障害者手帳の交付対象となります。
| 等級 | 詳細 |
| 1級 | ・機器への依存が絶対的な状態(クラス1)でペースメーカー等を体内に入れた人 ・機器への依存が相対的な状態(クラス2)でペースメーカー等を体内に入れ、身体活動能力が2メッツ未満の人 |
| 3級 | ・クラス2以下の状態でペースメーカー等を体内に入れ、身体活動能力が2メッツ以上4メッツ未満の人 |
| 4級 | ・クラス2以下の状態でペースメーカー等を体内に入れ、身体活動能力が4メッツ以上の人 |
精神的なストレスによって、脈拍が速くなったり、血圧が上昇するなど、心臓機能への影響は大きいといえます。
 kaigo clover
kaigo clover 

