この記事はで読むことができます。
世界の定義

世界保健機関(WHO:World Health Organization)によると、65歳以上を高齢者として定義しています。
日本の定義

日本では、一般的に65歳以上を高齢者として定義しています。
さらに65歳以上の高齢者を以下のように区分けしています。
- 前期高齢者(65〜74歳)
- 後期高齢者(75歳以降)

85歳以降を「超高齢者」とすることもあります。
老化とは
人は生まれてから死ぬまでに、様々な変化を迎えます。
「成長」や「発達」と呼ばれることもありますが、成熟期以降は「老化」と呼ばれるようになります。
老化とは、成熟期以降に起こる身体・生理的な機能の変化(主に衰退)を表す言葉になります。
加齢との違い
「老化」も「加齢」どちらも身体機能の変化を表す言葉ですが、意味合いは少し異なります。
- 【加齢】生まれてからどれだけ時間が経過したか
- 【老化】加齢に伴い、身体・生理的な機能が衰えること
加齢は、時間の経過によるポジティブな変化を含むこともありますが、
老化には、衰えのようなネガティブな意味合いが含まれることも多いです。
老化のメカニズム
老化のメカニズムとして、現在ではいくつかの説が取り上げられています。
代表的なものについて見ていきましょう。
自然崩壊説

すべての物質はやがて崩壊し、消滅するという自然の摂理と同じように人体も崩壊し、消滅に向かっていくという考え方。
遺伝子プログラム説
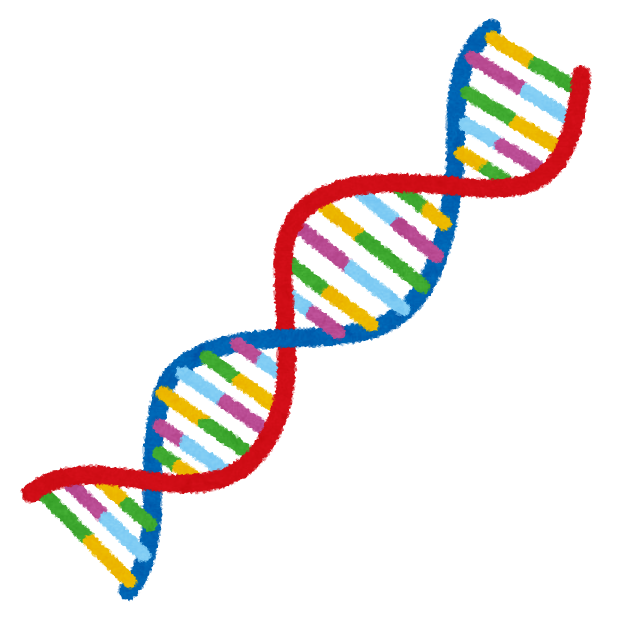
人の細胞には、細胞分裂ができる限界があるという考え方。

多くの学説がありますが、それぞれが独立しているのではなく、相互に関係しあっているという考え方が主流になっています。
人格と尊厳
日本国憲法第13条には、「すべての国民は、個人として尊重される〜」とあります。
つまり、私たち一人ひとりは「人格」を尊重される権利を持っています。
しかし、高齢者や障害者など「支援が必要な人」の人格については、尊重されていない場合があるのも事実です。
なぜそういった事が起こるのかというと、私たちは自分が所属していない集団や年齢層について思い込みや偏見を持っていることがあるからです。
「年を取れば誰でも穏やかになる」
「高齢者は恋愛をしない」
このように年齢を理由にした偏った見方のことを「エイジズム」といいます。
エイジズム(バトラー提唱)
「年を取っているという理由で高齢者を1つの型に当てはめて差別すること」
こうした偏った見方をしないためにも、
- 偏見を持ちやすい傾向があることを知り、自身の考え方を顧みること
- 高齢者一人ひとりの人生、家族、考え方を知ること

高齢者を一人の個人として尊重し、尊厳を持って接することが介護福祉職には求められます。
老いの価値
喪失体験
喪失とは
老年期になると様々な喪失体験に直面します。
喪失体験
「年を取ることで起こる身体や心、環境などの変化によって、今まであったものが失われていくこと」
大切な家族・友人の死だけでなく、体力の低下、収入の減少といった出来事から、喪失を感じることもあります。
喪失と感じるかどうかは、個人によって差があるので、出来事そのものよりも、どのように感じているのかを考えることが大切です。
老年期に起こりやすい喪失体験の例は以下のとおりです。
- 健康面の喪失(病気、入院、認知症など)
- 人間関係の喪失(死別、施設入所、家族介護など)
- 経済的な喪失(退職、年金など)
- 役割の喪失(子どもの自立、退職など)

特に高齢者の場合、喪失体験から生じるストレス反応が身体機能の低下にも繋がりやすいです。
悲嘆とは
精神分析学者のフロイトは、死別後の心理過程を「悲嘆」といいました。
悲嘆
「大切な人を失ったときに生じる悲しみ」
この悲嘆が癒やされ、穏やかな心理状態へと戻っていく過程を「悲嘆過程(モーニング・プロセス)」といいます。

悲嘆過程は、誰にでも起こりえる正常な心のプロセスといえます。
また、愛着理論を提唱したボウルヴィは悲嘆過程を4つの段階に分け、それら4つの段階には「順序性」があることを示しました。

現在では、悲嘆からの回復には「個人差が大きいこと」「周囲や社会からのサポート」も重要だと考えられています。
二重過程モデル
心理学者のストローブとシュト(Stroebe & Schut)は死別後の心理過程について、「二重過程モデル」を提唱しました。
これは「喪失志向」「回復志向」という2つの側面を行き来しながら、死別後のストレスに対応するという考え方になります。


高齢者が迷いながら(ゆらぎながら)決めることができるもので、高齢者のペースに合わせてサポートすることが大切です。
 kaigo clover
kaigo clover